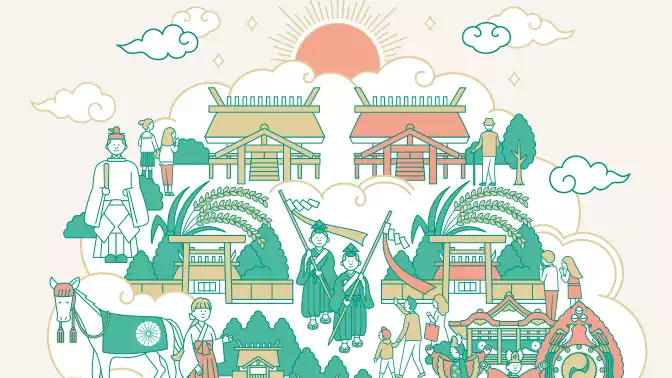知るKnow
神宮の御料と御料地

神々に捧げられる
神饌となる御料、由緒ある
御料地で自給自足
神饌など神々へのお供え物を御料、そして御料を調達する場所や施設を御料地と呼びます。
神宮には、神嘗祭を中心に年間1500回に及ぶお祭りを滞りなく行うため、神宮神田、神宮御園、御塩浜などの御料地があり、神様に捧げられる品々は古儀を尊重して清浄に調製されます。
尚、各御料地とも立ち入ることはできません。
神様のお食事
「日別朝夕大御饌祭の神饌」
朝と夕の二度、日々奉られる神饌は御飯三盛、御塩、御水、乾鰹、魚、海藻、野菜、果物です。それらの神饌や神饌を盛りつける素焼きの土器も神宮で作ります。

神宮のお米と
野菜
- 神宮神田
- 三重県伊勢市楠部町
- 神宮御園
- 三重県伊勢市二見町溝口
神田・御園ともに一般の方の見学はできません。

五十鈴川の水をいただき、
神宮神田と神宮御園で
清浄に育つ
神宮神田の歴史は古く、2000年前に倭姫命がお定めになったとの伝承があります。神田では五十鈴川の水をいただき、神宮のお祭りにお供えされる御料のうるち米ともち米が清浄に育てられ、その年にとれた新米は神嘗祭で天照大御神に奉られます。
神宮御園では季節に応じた野菜果物を栽培し、その品目は多種にわたります。
神宮神田について
神田では多くの品種を育て、また田植えは時期をずらして行います。それは、天候不順や台風などの被害を最小限にとどめるためです。
神田では、稲の育成の節目に豊かな稔りを願うお祭りも行われます。4月には神田下種祭、5月には神田御田植初、9月には抜穂祭が古式ゆかしく行われます。
-

5月上旬 神田御田植初 -

9月上旬 抜穂祭
神宮御園について
神宮御園では、神宮のお祭りにお供えする野菜・果物を栽培しており、その品目は50種類ほどあります。
お供えされる野菜や果物は、お祭りによってその品目と数量が決められています。また、盛りつける土器の大きさも決められているので、それにあった大きさに育てるよう細心の注意がはらわれます。
毎年春分の日には御園祭が行われ、豊かな稔りと農作業に携わる人々の作業の安全が祈られます。

神宮の御塩
- 御塩殿・御塩汲入所・
御塩焼所 - 三重県伊勢市二見町荘
- 御塩浜
- 三重県伊勢市二見町西

お祓いにも 用いられる御塩、
御塩浜・御塩殿で作られる
神宮では生命の源である米・塩・水は太古から天照大御神の大切なお供えとされてきました。その中でも御塩は、神饌[1]として捧げられるだけでなく、お祭りの前のお清めの塩としても用いられ、欠かすことのできないものです。
神宮では五十鈴川の河口近く、二見浦で御塩を作っていますが、これは内宮御鎮座当時、倭姫命がお定めになったと伝えられています。
- [1]神饌とは主食の米に加え、酒、海の幸、山の幸、その季節に採れる旬の野菜などを調理して、神様へお供えされる食事です。
神宮の御塩作りについて
諸外国の多くが岩塩であるのに対して、わが国の塩は国土の四方が海に囲まれていることを活かし、海水から採取したものが主流です。海水から効率よく塩を採ることが追及される中、神宮では昔ながらの入浜式塩田法を用いて作られています。その工程は1.採鹹作業、2.荒塩作り、3.御塩焼固の三つに分けられます。
- 1.採鹹作業
- 毎年7月下旬の土用の頃、御塩浜で鹹水と呼ばれる高濃度の塩水を採取します。御塩浜は海水と淡水が混じる場所にあり、その理由は海水に少し淡水が和合した方が良い塩ができることによります。鹹水は約1週間かけて採取されます。

- 2.荒塩作り
- 採取された鹹水は御塩汲入所に運び、すぐ隣にある御塩焼所において鉄の平釜で炊き上げて荒塩にします。この作業は交代で火を焚き続けながら、一昼夜かけて行われます。

- 3.御塩焼固
- 毎年10月5日に御塩殿神社において御塩殿祭が行われ、御塩焼固の安全と日本の塩業の発展が祈念され、その後5日間にわたって焼固が行われます。荒塩は御塩殿で三角錐の土器につめて焼き固め、堅塩に仕上げます。御塩焼固は10月と3月の二度行われます。

神様の衣「神御衣」
- 神服織機殿神社・
八尋殿 - 三重県松阪市大垣内町
- 神麻続機殿神社・
八尋殿 - 三重県松阪市井口中町

神御 衣祭で奉られる
「神様の衣」、機殿の
二神社で織り上げる
神様の衣を「神御衣」といいます。神宮では毎年春と秋、天照大御神に和妙と呼ばれる絹と荒妙と呼ばれる麻の反物に、御糸、御針などの御料を添えてお供えする神御衣祭が行われています。そしてお祭りに先立ち、和妙は神服織機殿神社、荒妙は神麻続機殿神社のそれぞれの八尋殿で奉織します。
機殿について
神服織機殿神社と神麻続機殿神社が鎮座する辺りは、古くから紡績業と関係が深く、神様に奉る絹や麻を奉織する服部神部と呼ばれる人々が住んでいたと伝えられます。
周辺の下御糸・上御糸・中麻績・機殿・服部などの地名からも、その関係の深さを窺うことができます。

機殿の由緒は古く、皇大神宮御鎮座当時に、五十鈴川のほとりに宇治の機殿を建て、天上の儀式にならって天照大御神の和妙を織ったことが伝えられ、その後、天武天皇の御代に紡績業の盛んな現在の地に移されたようです。
現在では神御衣祭を控えた5月と10月に神宮から神職が参向し、それぞれの八尋殿で奉織が行われます。奉織の前後には神御衣奉織始祭、神御衣奉織鎮謝祭が行われます。

神宮のあわび・干鯛・土器

祭典でお供えされる海の幸、
大切に調えられる
素焼きの器
神宮のあわび
- 御料鰒調製所
- 三重県鳥羽市国崎町
一般の方の見学はできません。
「あわび」は一般的には「鮑」、「蚫」と書きますが、神宮では『延喜式』に則って「鰒」と書きます。 鰒調製所の歴史は古く、その起源は約2000年前に倭姫命が志摩の国を巡られていた時、国崎の海女が鰒を差し上げたことから御贄処[1]として定められたと伝えられます。
- [1]御贄処とは皇大神宮へ奉るお供え物を採る所。
国崎の鎧崎にある木造平屋建ての調製所は、潔斎場と呼ばれる身を清める所があり、作業は清浄を期して行われます。また調製所のさらに高い所には鰒干場があり、現在でも昔の手振りそのままに、身取鰒、玉貫鰒が調製されています。

神宮の干鯛
- 御料干鯛調製所
- 愛知県知多郡知多町大字篠島
一般の方の見学はできません。
神宮の土器
- 土器調製所
- 三重県多気郡明和町蓑村
一般の方の見学はできません。
土器調製所は多気郡明和町蓑村にあります。この付近は神代の昔、高天原[1]から埴土を移したという伝承があり、良質な粘土に恵まれ、皇大神宮御鎮座当時から土器を作ってきたと伝えられます。
- [1]高天原とは『古事記』などの日本神話で天津神が住む天上界をさします。
現在でも土器調製所では、様々なお祭りに使用される素焼きの土器を年間約60,000個調製しています。神宮では一度使われた土器は再使用せず、細かく砕いて土に返すことになっています。